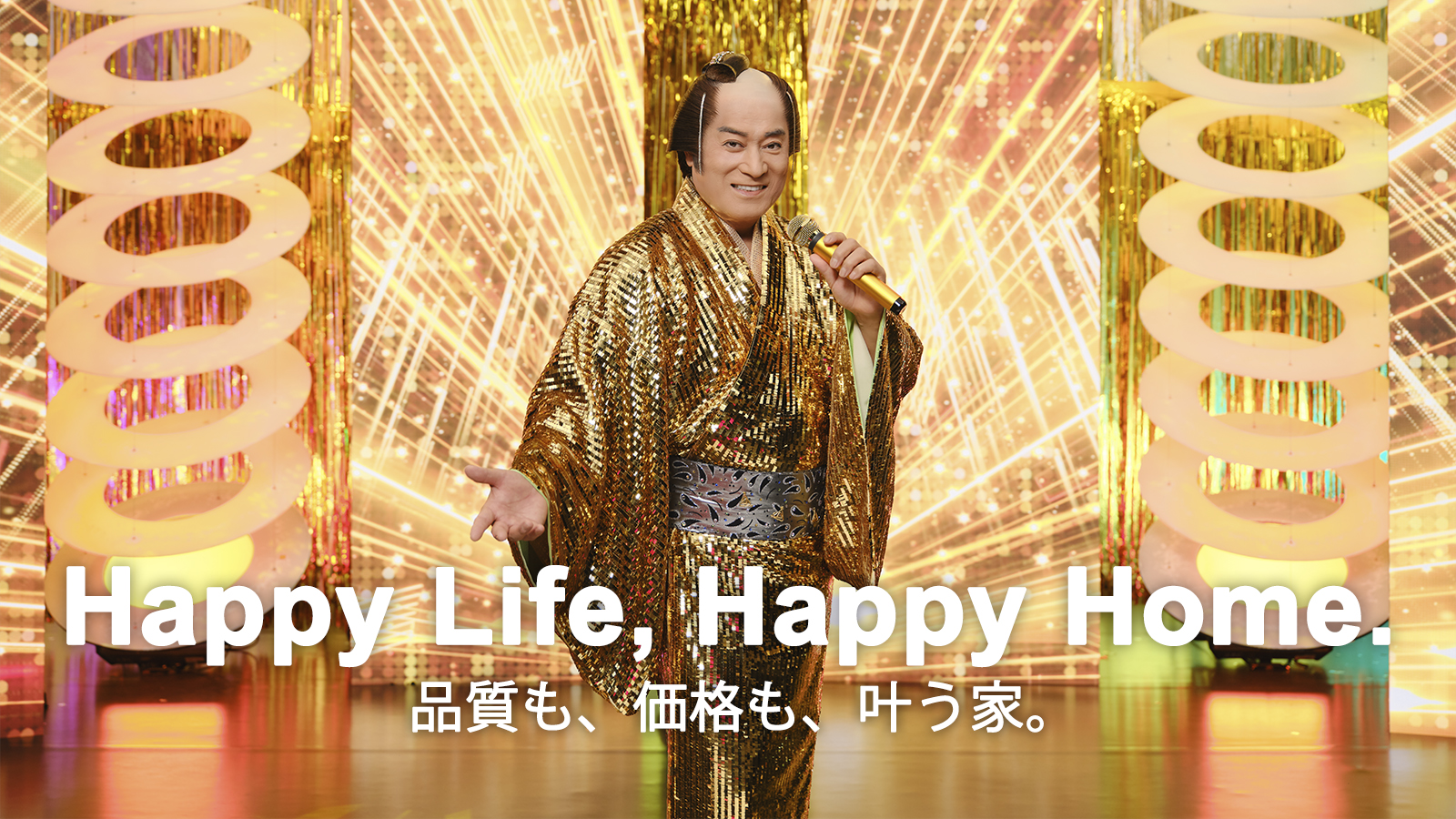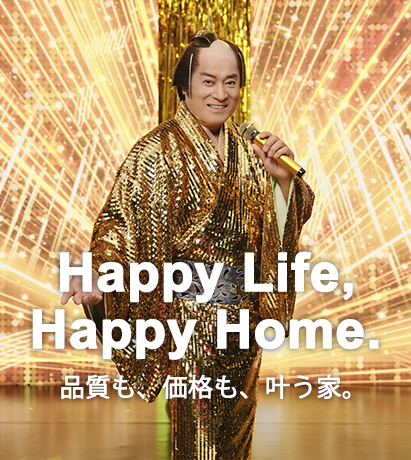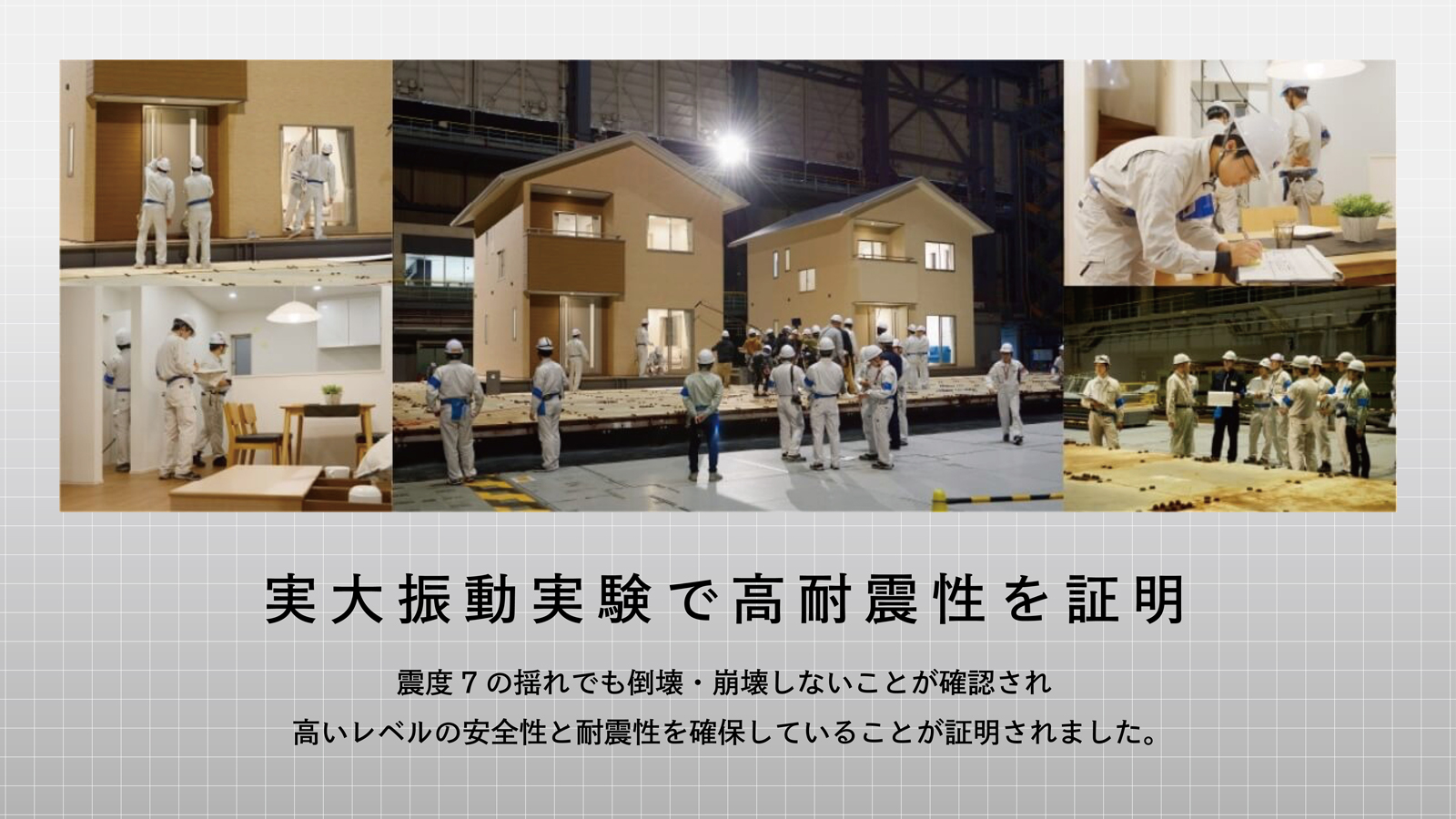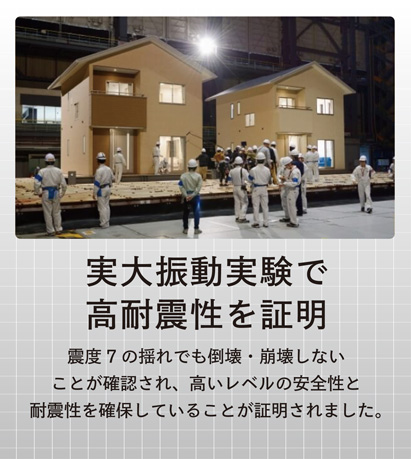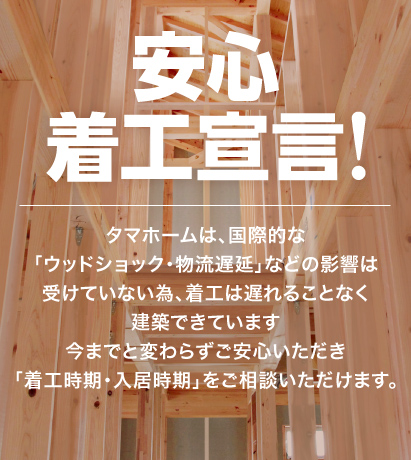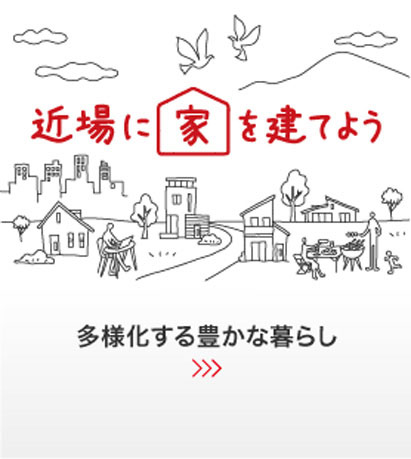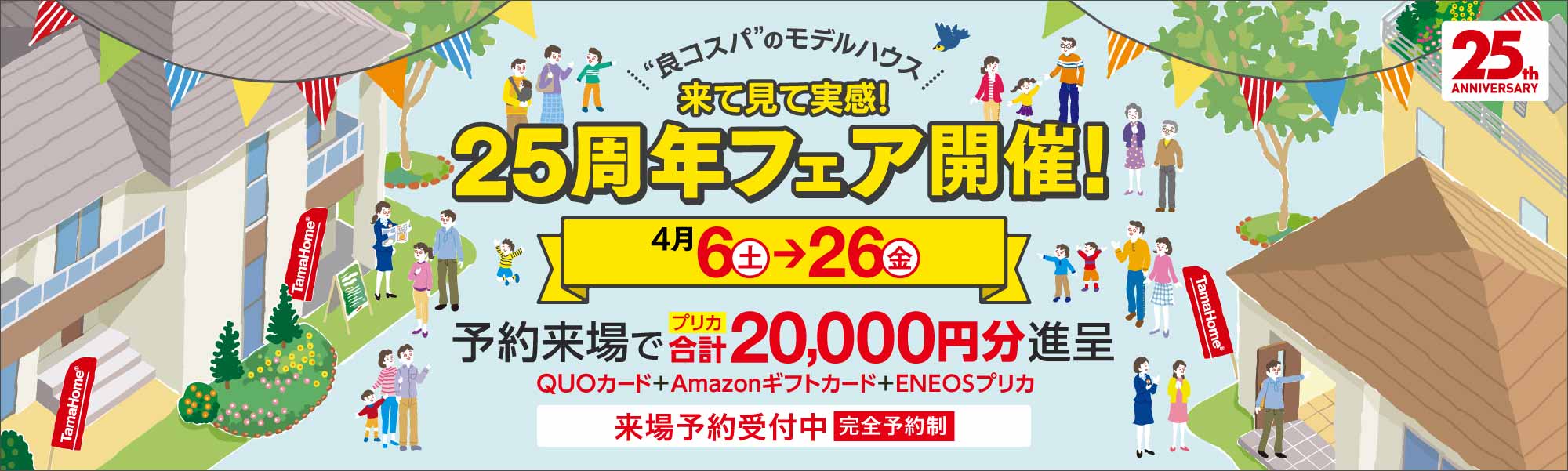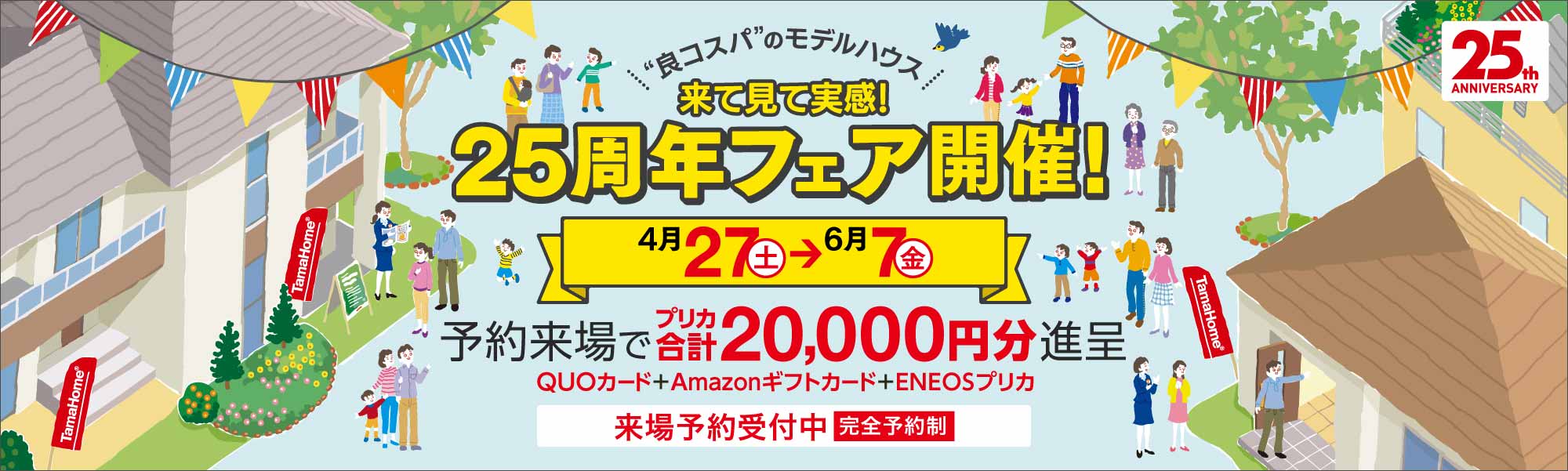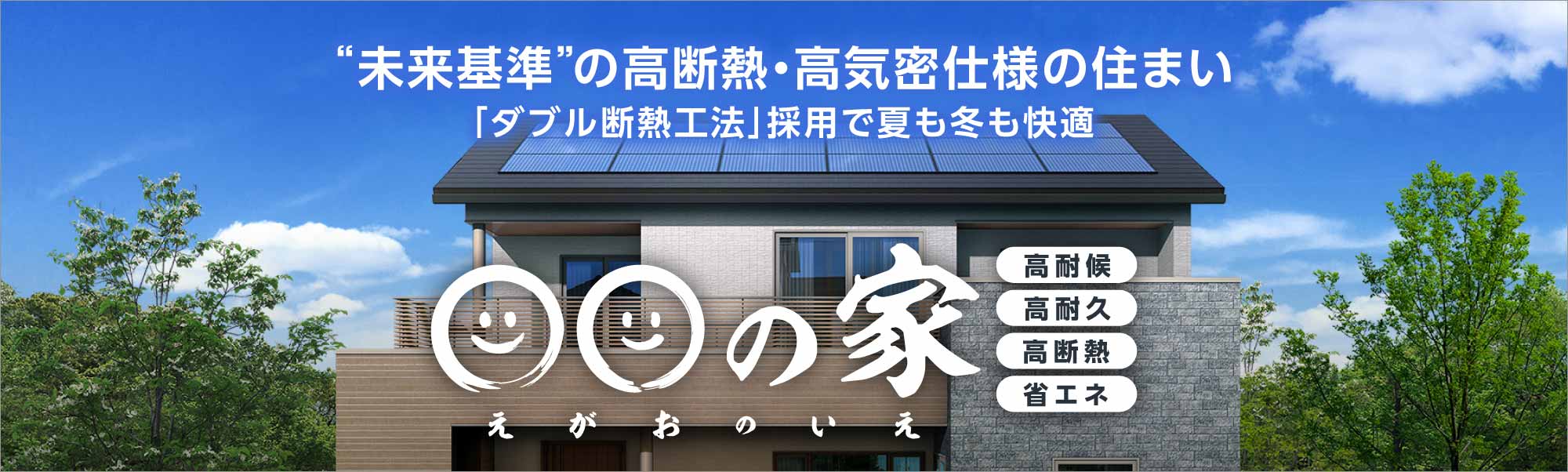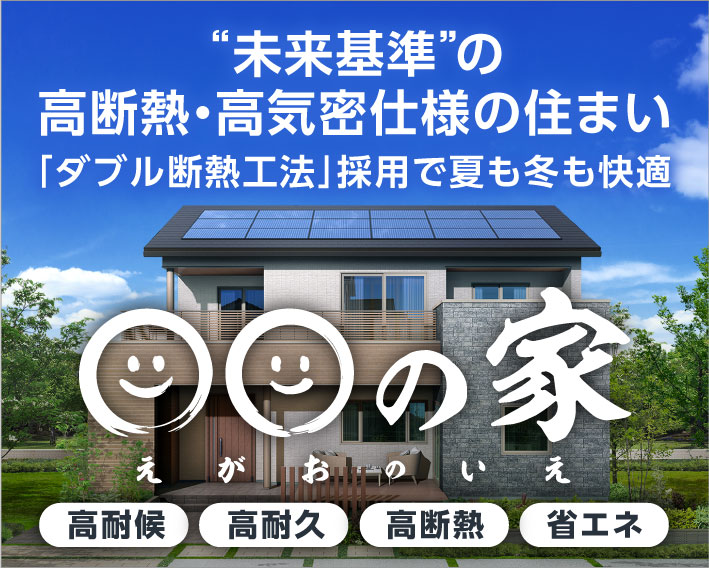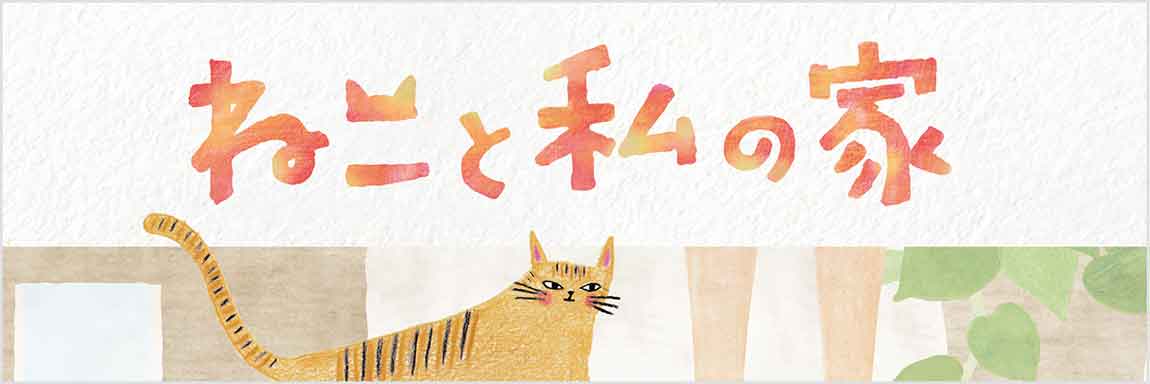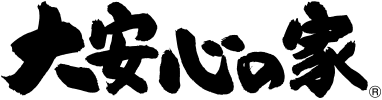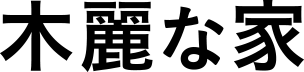お知らせ
タマホームで
自由設計の家づくり
商品ラインナップ
良質低価格の家だから
夢にこだわれました
タマホームオーナー様の声

20代のTamaHome
日々の生活が豊かになり、周囲との人間関係が深まり、
子育ての環境が向上する「一戸建て」には、確かなものがあります。
充実した暮らしを手に入れるために、
「20 代で家を建てる」について考えてみませんか?